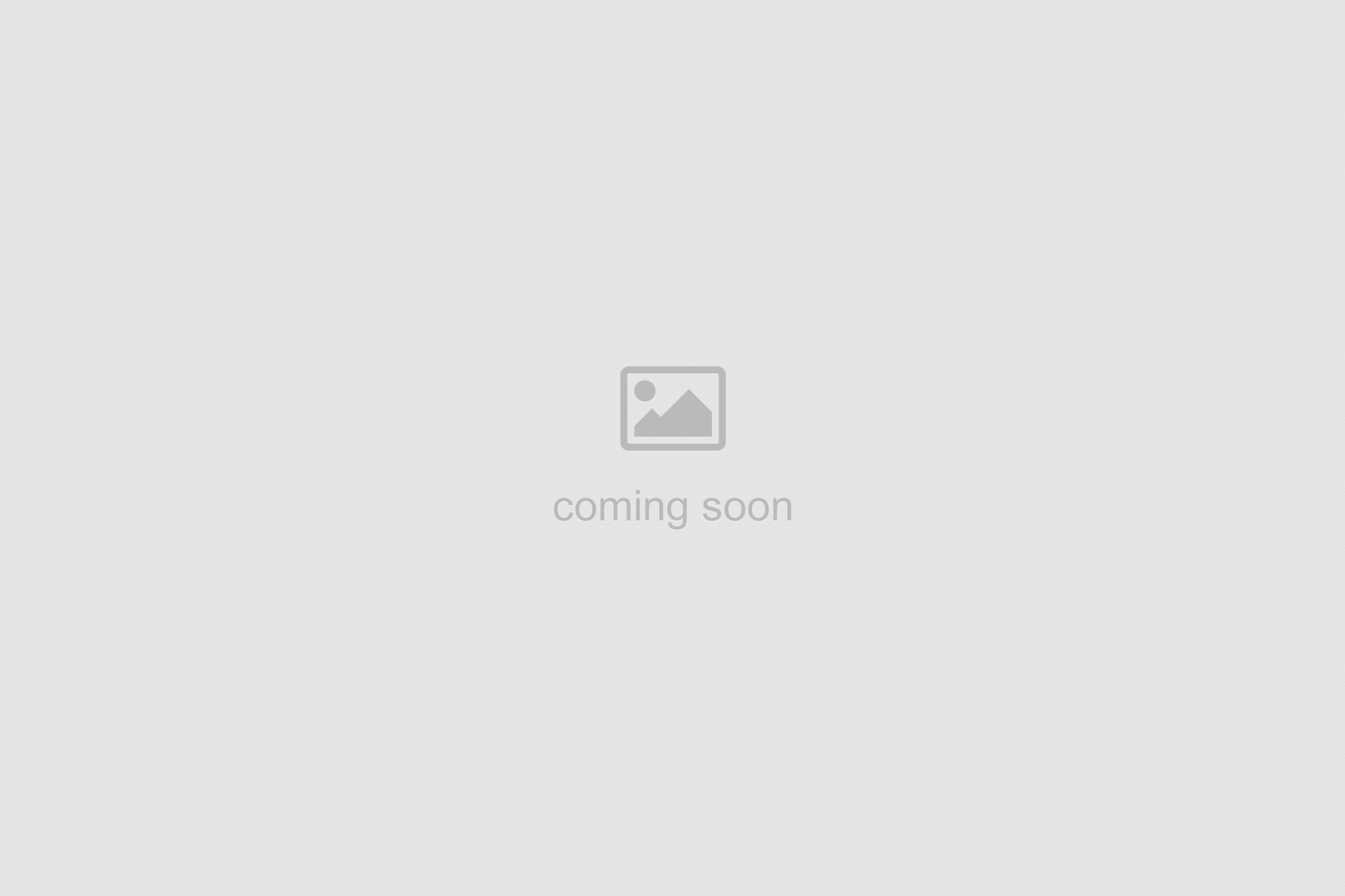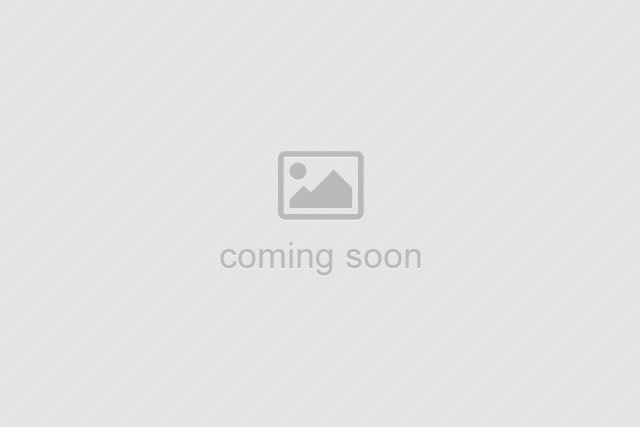安心・安全のデンタルサポート
みなさまと共に考え「日々の生活の幸せ」を歯科を通してサポートするために私たちは努力します。
私たち医療法人原田歯科スタッフはみなさま一人ひとりに向き合い、つねに求められるよきパートナーとして地域や社会に貢献してまいります。このホームページから「当院のご案内」「歯科に関する情報」など、みなさまのお役に立てるタイムリーな情報をお届けします。
医療法人原田歯科からの新着情報やお知らせ
2024-04-01
2024-04-01
2019-12-26
2018-04-23
| RSS(別ウィンドウで開きます) |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (13:00まで) | 休診 |
午後 14:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 | |
※最終受け付け時間は診療終了30分前になります。 ※休診日・・・毎週土曜日午後、日曜、祝祭日、年末年始 ※○健診・公務出張などで臨時休診する場合があります。 | |||||||
診療のご案内
はじめて受診される方はお読みください。
診療メニュー
当院で行っている診療科目になります。